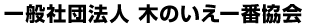森と木と建築のつながりを体感する一日
―「緑と水の森林ファンド体験セミナー」を高尾で開催
2025年6月13日、高尾山口駅周辺にて、これからの建築業界を担う若い設計者や建築関係者を対象とした体験型セミナーを開催しました 。テーマは「自然や街並み の景観と調和した建築の木質化」。気候変動への対応や国産木材の活用が注目される中、木質化・木造建築の見学、日本の森林に関する講義、そして実際の森林散策を通じて、木材利用の意義を知識と体感の両面から深めるプログラムとなりました。参加者にとって、これからの建築における木材活用の可能性を考える、貴重な一日となりました。
- 実例見学と森林体験を通して木材利用の意義を知り、考える
- テーマ1:木造・木質化建築と街並みの景観との調和を学ぶ ― 高尾山口駅と周辺施設を訪ねて
- テーマ2:木材利用の意義を学ぶ ― 木造展示施設で「設計者等のための森林教室」を受講
- テーマ3:森を歩き価値を体感する ― 高尾の自然にふれる自然研究路6号路の散策
- 自然との対話がもたらす、建築設計への新たな視点
実例見学と森林体験を通して
木材利用の意義を知り、考える
実際に歩き、観察し、体感することで、木材利用の意義について理解を深めることを目的とした本セミナー。以下の3つを目標に掲げ、プログラムを構成しました 。
- 自然環境・街並みの景観と調和した木造・木質化のあり方を考える。
- 木材や木質建材を使用する意義を、森林・林業・地域経済の観点から考える。
- 木材・木質建材の起源となる森林環境の中で、樹木や森林の機能を体感し理解を深める。
木造建築の見学や森林散策を通じて、木材利用の意義や森林の多面的な機能を「見て・触れて・感じる」ことができるよう設計された、約3時間の体験型セミナーとなりました。集まった若い建築 設計者・建築関係者は、今後の建築における「木」との向き合い方を考える上で、多くの学びを得る機会となりました。

テーマ1:木造・木質化建築と街並みの景観との調和を学ぶ
― 高尾山口駅と周辺施設を訪ねて
セミナーの前半では、木質化の取り組みと、周囲の自然・街並みの景観との調和について学ぶため、高尾山口駅とその周辺の木造施設を訪れました。

最初に、京王電鉄のご担当者様からご案内いただいたのは、 2015年に木質化リニューアルされた京王電鉄高尾山口駅。 木材をふんだんに使った駅舎は、今年で改修から10年を迎えます。高尾山の持つ魅力を木材の多彩な仕上げによって表現することで、ワクワクするような地域のシンボルとなる駅舎が実現されています。改修当時の背景や木質化のコンセプト、使用された木材の特徴、そしてリニューアル によって得られた効果についてお話いただきました。

鉄道高架部はRC造、大屋根部は鉄骨造で、木はあくまで意匠として取り入れており、公共性の高い建築として外装の木材には難燃性の塗料を使用しているとのこと。 ピロティだけでなくコンコース内まで入らせていただき、日本の伝統建築から複数の仕上げ方法を引用するなど、多彩な木のあしらいが取り入れられていることを知ることができました。この駅舎は高尾山の玄関口として、リニューアルされ た点が高く評価されているそうです。

竣工から10年経過後のメンテナンス上の課題など、現場の視点を交えた貴重なお話も伺うことができました。木である以上経年変化は免れず、見栄えの問題も出てきているとのこと。そこで4年ほど前、一部の外壁の表層を薄く削り、新たにカビを抑制する高耐久塗料を試験施工 してみたそうです。その部分は現在も美観を維持できているため、今後全体への施工も検討されているそうです。近年の木質化の取組として京王電鉄で木材を 使用した最初の施工例であり、現在明らかになった課題に取り組んでいる最中であるとのことでした。

その後は、駅周辺に点在する宿泊施設や 、木造店舗・寺院・展示施設を巡りながら、各施設の木の使い方やメンテナンスの工夫、経年による変化のあり方について見識を深めました。どの建築も、単に木材を使っているだけでなく、自然や街並みの景観と の調和を意識した設計がなされており、「風景に溶け込む木造建築」が実現されていることを実感できるひとときとなりました。


テーマ2:木材利用の意義を学ぶ
― 木造展示施設で「設計者等のための森林教室」を受講

セミナーの中盤では林野庁関東森林管理局 高尾森林ふれあい推進センターを訪問し、木材利用の意義について深く学ぶ時間が設けられました。まずは、センター内の木造展示施設を見学。実際に木材を使用して建てられ、太い杉の柱が並ぶ空間に足を踏み入れることで、木が五感に訴える魅力を体感しました。

続いては、センターの所長である山田徹氏によるレクチャーを受講しました。冒頭では、日本の国土における森林の割合や、人工林の多くが収穫期を迎えているという基礎的な情報から始まり、森林を取り巻く現状についてわかりやすくご解説いただきました。
森林が果たす多面的な機能については、木材の生産だけでなく、水源涵養、土砂災害の防止、地球温暖化の抑制、環境保全、生物多様性の維持といった環境面での貢献、さらにはレクリエーションや癒しといった文化的機能まで広く紹介されました。私たちの暮らしは、想像以上に多様なかたちで森林と結びついていることを、改めて実感できる内容でした。
後半では、木材の伐採から利用までのサイクルや、林業が直面している課題、特に獣害や担い手不足 といった問題に触れつつ、国産材利用の重要性とその新たな展開についても紹介。設計や建築の現場で国産材を活かすことが、森林の健全な育成と持続可能な地域づくりにつながる――そんな力強いメッセージで締めくくられました。
木を使うという選択は、単なる素材選びではなく、森林を育て、地域社会や地球環境を支える行為でもある。この考え方は、参加した建築設計者にとって大きな気づきとなりました。

テーマ3:森を歩き価値を体感する
― 高尾の自然にふれる自然研究路6号路の散策
セミナーの締めくくりは、森林に実際に足を踏み入れ、五感でその価値を体感するプログラムです。舞台は「自然研究路6号路」。現地案内は、弊社の専務理事である安永正治(自然体験インストラクター )が務めました。

散策は、ケーブルカー清滝駅前からスタート。冒頭は高尾山の成り立ちと森林の歴史について詳しく解説しました。奈良時代から信仰の対象として守られ続けたこの山は、江戸幕府に よる保護や、戦中・戦後の伐採、そして1967年の国定公園指定と、長い歴史の中でさまざまな変遷を経て今に至ります。現在ではミシュラン・グリーンガイドで三つ星を獲得し、国内外から多くの人々が訪れる場所となっています。


散策の途中では、人工林と天然林の違いや、森林が持つ水源涵養、生物多様性の保全、災害防止などの多面的な機能についても説明しました。特に高尾山は、暖温帯と冷温帯の境界に位置しており、1,600種もの植物、100種以上の鳥類、30種以上の哺乳類が確認されるなど、日本有数の生物多様性を誇る森林であることを紹介しました。
また、森林の“緑のダム”としての役割も解説。雨水が地中にしみ込み、岩盤層でせき止められながら少しずつ湧き出す仕組みにより、豊かな水資源が保たれています。木々の根が網や杭の ように土壌を支える構造や、植物の多様性が山全体の安定性に寄与している様子も、実際の景色を前にした解説だからこそ、説得力をもって参加者の心に届いたようです。

終盤には、森林を歩くことがもたらす心理的・生理的効果についても紹介しました。森の中を歩くことで副交感神経が優位になり、ストレスが軽減されることが科学的に証明されており、眺めるだけでも効果があることがわかっています。建築の観点だけでなく、健康や暮らしの質にも森林が関わっていることを、再認識していただけたと思います。
自然との対話がもたらす、建築設計への新たな視点
「実際の森に足を運ぶことで、講義で学んだ内容がより深く実感できた」という参加者の声が印象的でした。机上の学びだけでは得られない気づきこそが、本セミナーの価値を象徴していたと言えるでしょう。
都市と山をつなぐこのプログラムは、建築と森林の距離を縮めるための第一歩。自然の中で感じたことを、これからの設計や素材選びにどう活かすか。参加者一人ひとりが、静かな森の中で思いを巡らせる機会となったなら幸いです。